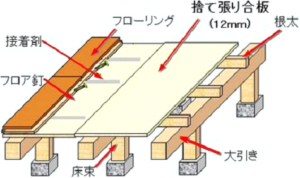いつも遺品整理士はミタをご覧いただきありがとうございます。
遺品整理士の堀川です。
先日テレビをつけると、名優として世間で名が知られ、志半ばに交通事故で亡くなった萩原流行さん。その奥様が、流行さんの遺骨を海洋散骨することを決意して海に散骨するまでに密着した番組が放送されていました。
萩原流行さんは生前から海洋散骨を希望されていたようですが、奥様はバイク事故のケジメがつくまで散骨に踏み切れなかったそうです。心の整理がつくタイミングは人それぞれですね。ほとんどの場合、散骨を決断するのは残された遺族です。故人が釣りが好きだったり、海に思い入れがあったり、故人の希望であったり色々な理由から海洋散骨を考えられると思います。散骨をすれば、自分のもとには残らないかもしれませんが、心の中や海を見れば永遠に故人の笑顔が残ると私は思います。
海洋散骨
散骨は、節度をもっておこなえば法的に問題はありません。日本における遺体の埋葬に関する規制は「墓地埋葬等に関する法律」で定められています。この法律では、自宅の庭など墓地ではない場所への遺体の埋葬を禁止していますが、散骨を禁止する規定はなく、一部地域の条例を除いて法規制の対象外とされています。故人が亡くなるとお墓に埋葬するのが当たり前のように考えられていますが、日本人は古来より亡骸を火葬して山や海に撒き、自然に還すという考え方が一般的でした。現在のように家族がひとつのお墓に入る風習は明治以降に広まった方法であり、ここ100年ほどに始まった新しい習慣といえます。
海洋散骨が増えている背景
海洋散骨を希望される方は10年前の2倍になっているそうです。これは最近になって、お墓に入るという固定観念から自由になり、人間が生まれた本来の場所である自然に還りたいと考える人も多くなったことが影響しているのかもしれません。また、現代社会における核家族化・少子化の進展により、特に都市部において、お墓の維持・取得に関わる問題・不安を抱えている人は多く、海洋散骨という方法は、そういったニーズにあっているとも言えます。自然環境保護への関心の高まりにより、野山を切り開いて墓地を作るよりは、遺骨を自然に還し、故人の眠る自然環境を大切にしていこうというエコロジー思想も背景にあります。