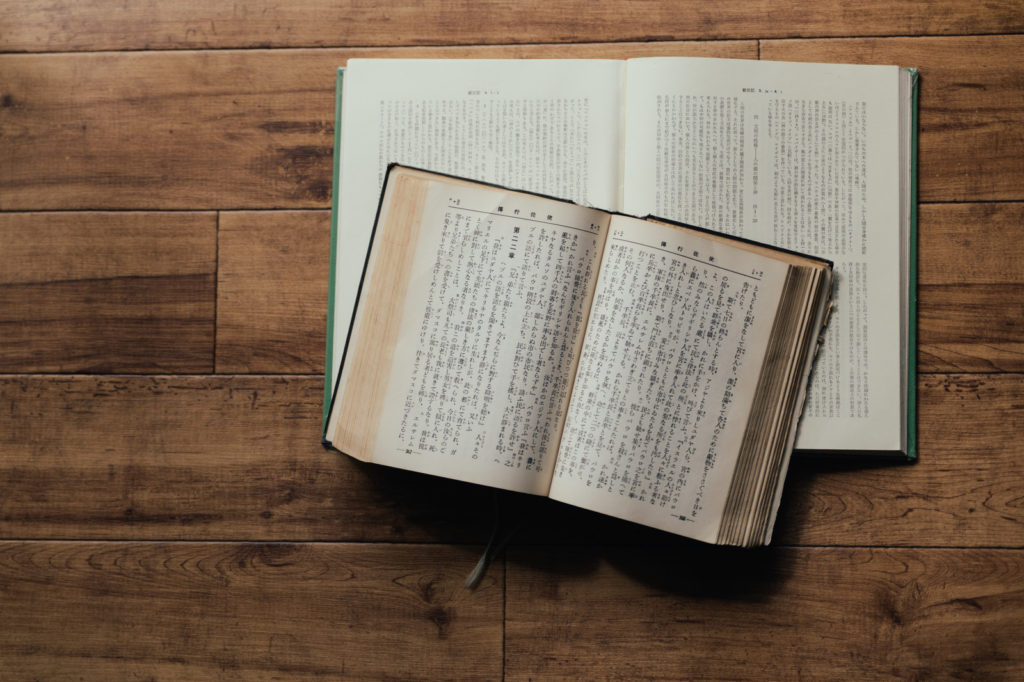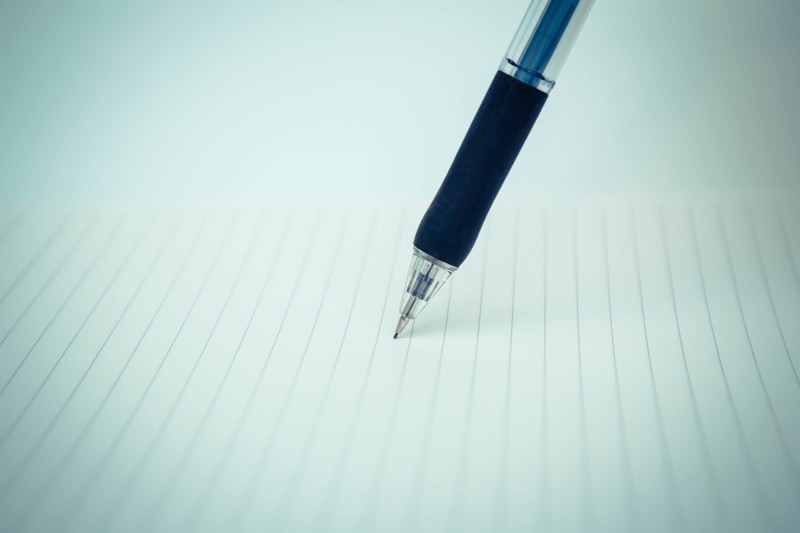
遺品整理士の堀川です。
自分がいなくなった後の遺族の負担を減らすために、生きているうちに身の回りの整理をしようと思う方が増えています。俗に「生前整理」や「老活」、「終活」と言われるものですが、やろうと思った時には体力がなくなっていたり、腕が上がらないということもあります。そんな時には業者を使うことも考えられるかもしれませんが、”エンディングノート”を活用する方法があります。エンディングノートは少し前からよく耳にするようになったものですが、「エンディングノート」という映画が公開されたのも大きな要因の一つでしょう。
このエンディングノートは自分に万一のことが起こった時に備え、あらかじめ家族やまわりの人に伝えたいことを書き留めておくものです。いなくなった後の家財や病気になった時に延命措置をしたいかといった医療面のこと、動けなくなった時の介護の方法、葬儀のスタイル、遺産相続、お墓のことなど様々です。
市販されているものや無料で配布されるものもあるので一度検討されてはいかがでしょうか。